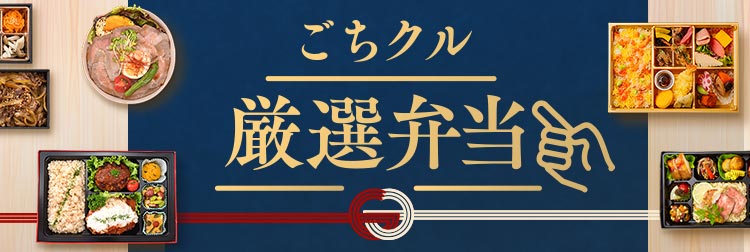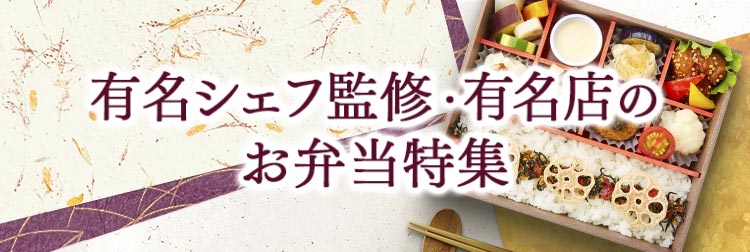葬儀・葬式の流れと手順
葬儀の流れや手順、葬式の段取りなど、ご臨終から、初七日や四十九日といった法事までの流れをご説明します。 「葬儀」というと、多くの人が通夜、お葬式、告別式を思い浮かべるかと思いますが、喪家・遺族にとってはそれだけではありません。ちなみに通夜とは、葬儀より前に遺族が故人の魂と寄り添いお別れするために過ごす夜をさし、葬儀は「葬式」と同義で、死者を葬るための儀式をさします。
全体の流れにはっきりとした決まりはありませんが、だいたいを頭に入れておくと、落ち着いて手配ができるのではないでしょうか。このページでは、葬儀・お葬式の流れに絡む細かな事柄とその手順を説明します。
法事・法要のお弁当をエリアで探す
割烹料理店の「懐石仕出し弁当」や、上品なお料理で人気の会席御膳弁当など、本格的なお食事を宅配弁当でお召し上がりいただけます。ご自宅や法事・法要の専門会場などでお食事(お斎)を召し上がる際の参考にしてみてください。
葬儀・葬式の流れ
葬儀・葬式のおおまかな流れや手順は下記のとおりです。
1臨終
死亡の確認と、医師から死亡診断書を受け取ります。
2ご遺体の搬送・安置
葬儀社に搬送を依頼し、ご遺体をお部屋に安置・遺体保全処置、枕飾りを整えます。
※病院提携の葬儀社に搬送を依頼した場合でも、葬儀の施行は、他の葬儀社への変更が可能です。
3寺院への連絡
通常は菩提寺や神社、教会に依頼しますが、菩提寺などがない場合は葬儀社が紹介します。
※失礼のない時間帯であれば、すぐに寺院へなくなったことを連絡しておくとよいでしょう。
4ご葬儀のお打ち合わせ
通常はご葬儀の内容や規模、返礼品や料理などを相談します。
打ち合わせは、なるべく喪主だけでなく他の人にも同席してもらうとよいと思います。
葬儀社は2〜3社ほど見積もりを取り、相談に乗ってもらうのもよいでしょう。
※失礼のない時間帯であれば、すぐに寺院へなくなったことを連絡しておくとよいでしょう。
5親戚・身内への連絡
連絡通夜・告別式の日程が決まり次第、リストに基づいて連絡します。
目上の方でも電話連絡で失礼にあたりません。電話の場合は、日程・場所を正確に。
式場への交通手段・最寄り駅などを確認しておきます。
6死亡届の手続き
市町村役場に「死亡診断書」を持参し、役場で「死亡届」の用紙を受け取りましょう。
※死亡届は死亡後7日以内に市町村役場に提出しましょう。
7喪主の決定・世話人の手配
喪主は、故人の血縁でもっとも近い人、またはその家を代表する人が務めます。基本的には配偶者、子供、兄弟の順です。
進行は葬儀社が行いますが、受付・会計などは金銭を扱うので、親族や信頼できる知人へ依頼しましょう。
8ご納棺(湯灌)
故人をお棺にお納めします。喪主をはじめ、遺族・親族の方々で旅支度をします。
副葬品のご希望がある場合、可燃物であることをご確認ください。
9通夜、通夜ぶるまい
通夜終了後、喪主または親族代表者が挨拶をします。
弔問客が帰られた後、残った遺族・親族・お手伝いの方々に食事を出します。
10葬儀、告別式、出棺、火葬
告別式は遺族・親族・会葬者がご焼香をし又、お花を入れてお別れをします。
お骨上げをされる方は、火葬が終了するまで火葬場の休憩所でお待ちいただきます。
11中陰(初七日)法要
中陰は初七日の法要です。
最近は火葬が終了した後に初七日の法要も済ませてしまう場合が多いです。
12四十九日法要
故人が亡くなってから49日目に骨納めをします。
魂は49日まではこの世に残っているといわれ、この日、骨納めをすることが多いです。
13年忌法要
一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・三十三回忌・五十回忌とそれぞれの年忌法要を営みます。
- 本来は四十九日の忌明けに行いますが、現在では、火葬場から戻った後に行う初七日法要の際に、 僧侶や世話役などの労をねぎらう宴席で「精進落とし」を行うことが一般的です。 なお、僧侶が席を辞退された場合は、「お車代」とは別に「御膳料」を包みます。
納骨・埋骨
中には火葬の当日、あるいは翌日に「埋骨」という例もありますが、一般的には初七日か三十五日、四十九日あたりに納骨、埋骨ということが多いようです。
墓地が間に合わないなどの事情で、たとえば初七日法要のあと霊園の納骨堂に「仮納骨」して、墓地が手に入り、墓が完成するのを待って、一周忌、または三回忌に埋骨するケースも少なくありません。
納骨・埋骨まで
火葬してから納骨または埋骨するまでの間は、自宅で朝・晩、供養します。仏壇の前とか床の間などに小机を用意し、白い布をかけ、そこに遺骨と位牌を安置します。線香、ろうそくを立て、お菓子や果物などを供えておがみます。
埋骨式
墓地に血族やとくに親しい人たちが集まって儀式が始まります。僧侶の読経・焼香のあと、近親者の手で土をかけて遺骨を墓に納めます。墓石ができるまでは仮の木の墓標を建てて、墨で、表に戒名、裏に生前の俗名と生年月日、亡年月日を書きます。
ただし、先祖の墓に合祀するのなら墓標は作らず、既存の墓石に、新しく戒名〈俗名〉、生年月日、亡年月日を追加で彫ります。埋骨式のために水、花、線香、ろうそくなどが必要ですが、都会の墓地では、墓地内にある花屋さんですべて用が足りるはずです。
埋骨式の後は、墓地内で茶菓を出したり、料亭でもてなしをしたり、自宅や仕出しのお弁当をふるまって参列者の労をねぎらいます。
ごちクルなら法事用宅配弁当を全国にお届け
法事や法要の際は、故人の思い出を語りあいながら食事をします。施主によっては料理店等を利用する場合もありますが、多くは仕出し料理や仕出し弁当の宅配サービスが利用されるようです。ごちクルの宅配弁当なら、本格的な仕出し料理を、煩わしい準備をすることなく、簡単にご用意できます。
法事・法要の仕出しをエリアで探す
オードブル、お子様向けメニュー、一品料理もご用意しておりますので、用途や年齢も幅広くご利用いただけます。仕出し+オードブルなど「仕出しにもう一品」の注文も実現可能です。
 お弁当デリバリー
お弁当デリバリー