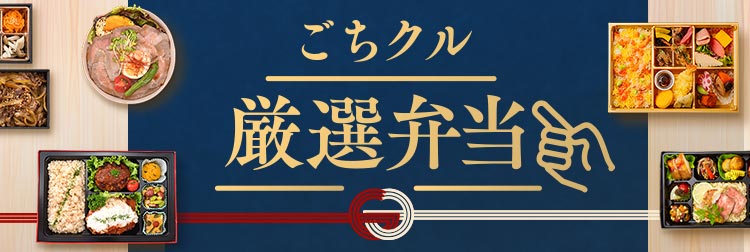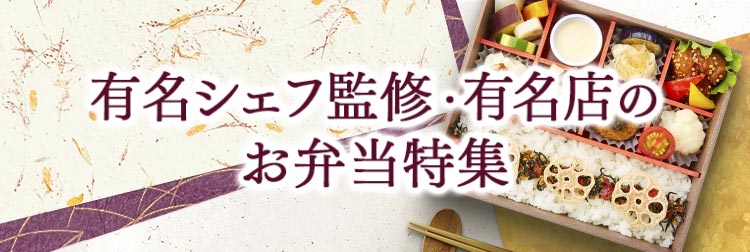法事の挨拶、献杯、席順・会場選び
法事の際の四十九日の挨拶や一周忌の挨拶、献杯の挨拶など流れやしきたり、会場選びや席順の決め方など迷うものが多くあります。三回忌や七回忌の際も同様です。法事での読経や焼香、法話やお参りはご供養に欠かせない法要です。加えてその後、食事をふるまい故人を偲ぶ会食(お斎)場は、改めて故人ゆかりの人々が思い出を語り合う大切なひとときとなります。
これらの法事・法要の「食事」は、一同が落ち着いて着席していただく場合がほとんどなので、取り分け式の会食料理ではふさわしくないとされる向きにあります。 お弁当や仕出し膳のようにひとり分がはっきりとしており、食べ始めと食べ終わりがしっかり区切れるものが好まれています。
法事・法要のお弁当をエリアで探す
割烹料理店の「懐石仕出し弁当」や、上品なお料理で人気の会席御膳弁当など、本格的なお食事を宅配弁当でお召し上がりいただけます。ご自宅や法事・法要の専門会場などでお食事(お斎)を召し上がる際の参考にしてみてください。
会場選びについて
法要会場による手配の違いをご紹介します。最近は自宅を避けて壇那寺や法事専門の会館の利用が一般的になってきました。
なお、自宅以外で法事を務める場合でも、自宅の仏壇は改めて掃除し、整えておきましょう。
法要専門会場
必要な仏具は整っています。御位牌だけを持参しますが、施主自身が用意するか、壇那寺から持参をお願いするのかを決めましょう。また、花や供物は施主が持ち込みます。
自宅や一般の貸し会場
自宅や自治会館等一般会場の場合、仏具と花、供物は全て施主が用意します。安置台も必要となります。壇那寺とよく相談しましょう。焼香等を嫌う会場もあるので、あらかじめ確認しましょう。
壇那寺の本堂
仏具その他は揃っていますが、やはり花や供物は施主が持ち込みます。規模感等は年忌によって異なるので、住職と相談するのが良いでしょう。
席順
法事や法要の食事での席次にも、上座下座があります。席順は、住職を最上座の主席に、次に親族(年長者から)や故人と特に親しかった友人の順にならび、施主とその家族は末席に座ります。
迷った場合は、年長者から上座をお勧めするのが良いでしょう。焼香の順とは異なる点に注意しましょう。
また、法事や法要の食事の場というのは、参列者だけでなく、お寺や導師(住職)へのお礼を伝える場でもあるので、住職をただ上座に祀り上げておけば良いというものではありません。施主は、席順だけでなく、食事中の会話の運びや、お弁当や料理に不備が無いか等も気配り、目配りをしなければなりません。
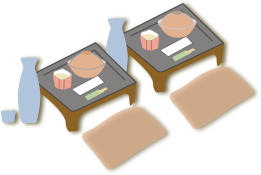
施主の挨拶
法事や法要は身内や縁者ほかゆかりのある方が集まる場なので、堅苦しいものである必要はありません。足を運んで供養に参列していただいた方々へのお礼の気持ちが肝要です。
はじめに
「本日はお忙しい中〇〇の法要にお越しいただき誠にありがとうございます」等、参列の感謝を述べます。また、参列者の心中のも配慮して、こここで施主とが、残された家族がしっかり力を合わせていくことを伝えることも重要です。
食事について
「本日は大変素志素養(しっそそよう=質素な食事のこと)ですが、故人を偲びながらごゆっくりご歓談ください」と、水を向けることで、次の「献杯」へ場をつなぎます。
※参列者は、着席後、次の献杯が終わるまでお弁当箱の蓋を開いたりすることはマナー違反です。
献杯(けんぱい)の流れ
法事、法要で食事を始める前に、「献杯」があります。慶事の際の「乾杯」とは意味もしきたりも全く違うので注意しましょう。
- 施主(遺族代表)から、乾杯の発声を行う人の紹介があったら、参列者は互いの盃にお酒や飲み物を注ぎます。施主に指名された人から献杯の挨拶を述べられます。
- 献杯の話し手から「献杯」という発声があります。「献杯」の意味は、敬意を表すために杯を捧げることなので、杯は静かに軽く上にあげるだけです。また、杯をカチンと鳴り合わせるのもマナー違反です。
- 出席者一同で、静かな声で「献杯(けんぱい)」と発声し、盃の飲み物に口をつけますが、完全に飲み干す必要はありません。拍手等もありません。
- 盃故人や神仏のへの敬意をさらに深める気持ちをもって、合掌と黙祷を捧げます。
- その後、施主からお礼の一言があります。その際「お食事をお召し上がりください」等の発声があります。これを機に、出席者が一斉にお弁当や仕出し料理に箸をつけるのがマナーです。
ごちクルなら法事用宅配弁当を全国にお届け
法事・法要はな仕出し料理ではなく、故人の好きなお料理を自由に選ぶことも可能です。
法事・法要の仕出しをエリアで探す
オードブル、お子様向けメニュー、一品料理もご用意しておりますので、用途や年齢も幅広くご利用いただけます。仕出し+オードブルなど「仕出しにもう一品」の注文も実現可能です。
 お弁当デリバリー
お弁当デリバリー